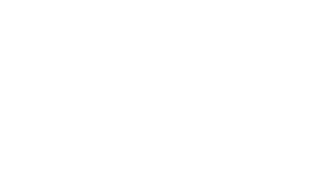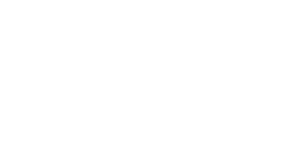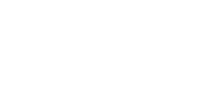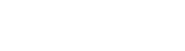情報共有メール・ビジネスチャットの例文を紹介! 書く時の注意点なども併せて解説!

メールの書き方に迷っていませんか。
「情報共有の目的と内容は理解しているけど、どのように送ったらいいのか迷う。具体的な例文を見ながら書きたい」といった場合に、そのまま使える例文をご用意しました。
今回はメールでの情報共有の際に役立つ例文と、注意点をご紹介します。情報共有のポイントを知って、業務の効率化につなげましょう。
Contents
情報共有メールがなぜ必要なのか
ではまず初めに、なぜ情報共有メールが必要なのかを解説します。
常に新しい情報が社内に渡るようにするため
社内の情報は常に新しくなくてはいけません。特に現代は情報の流れが早く、常に新しい情報にアンテナを張ってキャッチアップしていかなければ、他の会社との競争に大幅な後れを取ってしまいます。
情報共有メールを活用すれば、だれか一人が新しい情報を手に入れたら、それを社内全体にいきわたらせることができます。つまり、社内の情報を迅速にアップデートしていくことが可能なのです。
業務の属人化を防ぐため
専門性の高い業務などでは特に業務の属人化が起こりやすく、そうなっても仕方がないケースもありますが、業務の属人化をそのままにしておくと業務のブラックボックス化が進みます。
しかし、情報共有メールを活用して常に情報共有をするようにしていれば、属人化を防ぐことができます。
また属人化の防止だけではなく、専門性の高い業務同士の情報交換によって技術のかけ合わせが起き、新たな技術が誕生することもありますよ。
コミュニケーションを円滑にするため
日ごろからコミュニケーションをとっている人なら問題ないですが、部署が違ったり、年が大きく離れていたりすると、コミュニケーションを取るのに少し壁を感じますよね。
ですが、情報共有メールである程度やりとりを行っている状態なら、そのような人とのコミュニケーションに対しての苦手意識が減るでしょう。
社内のコミュニケーションを円滑にするためには、まずは(情報共有)メールを使ってコミュニケーションを取ると良いでしょう。
情報共有が上手くいくメールの例文
情報をうまく共有する際は、いくつかのポイントを押さえたうえでメールを作成することが大切です。メールの例文を紹介いたしますので、定型文として活用してみてください。
日報を送る場合
日報を共有するときは「報告事項の整理」「1日を通して得た成果の共有」の2点に注意して作成しましょう。
——————
件名:6月1日(水)日報名前
本文:
〇〇課長
お疲れ様です。営業部の〇〇です。
本日の業務について、以下の通り報告いたします。
【本日の業務内容】
9:00朝礼後、メールチェックと返信
9:30営業先に移動(△△駅〜△△駅)
11:00〇〇社納品(製品番号:00000)
13:00〇〇社定期訪問新商品の案内
14:30移動時間(△△駅〜△△駅)
15:30帰社
16:00ミーティング
17:30〇〇社向けの提案資料作成
18:00退社
【報告事項】
〇〇社より現在発注いただいている商品(製品番号:00000)についてご意見をいただきました。詳細内容は添付ファイルにまとめておりますので、ご確認よろしくお願いいたします。
進捗を報告する場合
進捗を報告するときは、「進捗状況」「目標の達成について」「目標との差異」の3点に注意して作成しましょう。
——————
件名:△△プロジェクトの進捗状況について
本文:
〇〇課長
お疲れ様です。営業部の〇〇です。
△△プロジェクトの進捗状況について、以下の通り報告いたします。
【売上】
1,000,000円
【目標達成率】
90%
【未達成の原因】
・店舗によって売上が大きく異なり、品切れになった店舗があった
・イベント当日に天候が悪くなり、期待していた集客が望めなかった
【今後の対応】
近隣店舗の連携を深め、在庫を共有するシステムを整える
議事録を共有する場合
議事録を共有するときは「議事録の日時」「議題」「決定事項」「課題」の4点に注意して作成しましょう。
——————
件名:6月1日(水)定例会議の議事録
本文:
営業部各位
お疲れ様です。営業部の〇〇です。
定例会議の議事録を作成いたしましたので、ご確認よろしくお願いいたします。
【日付】
6月1日(水)14:00〜15:00
【議題】
週刊報告と6月の営業目標
【決定事項】
・コンペのテーマと開催日時
・8月から導入する情報共有ツールの運用開始日
【今後の課題】
社内SNS担当責任者の選定
情報共有メールを書く際のポイント
情報共有は目的によって伝えるべき内容は変わりますが、共通して気を付けるべきポイントがあります。
具体的に紹介いたしますので、誰もがわかりやすく見やすいメールを心がけましょう。
件名をわかりやすく工夫する
普段のメールでも注意すべきポイントですが、社内の情報共有を行う際のメールでも件名はわかりやすく工夫を行ってください。
件名を確認しただけで、メール本文の大まかな内容を想像できるのがベストです。業務が忙しくなると、件名で確認不要と判断する方は珍しくありません。
情報の読み飛ばしを防ぐためにも、件名では「誰が」「何を」伝えたいのかをしっかりと記載しましょう。わかりやすい件名を設定すると、検索しやすくなるのでメールの見落としも防ぐことができますよ。
CCの付け方に気を付ける
情報共有を行う際は、CCの付け方にも気を配るようにしましょう。
CCを付けるケースは「チーム内で同時に報告したい場合」と「他の人にも内容を共有したい場合」が基本です。しかし、CCを使うときのニュアンスには「直接やりとりをする必要はないけれど、念のために情報を共有しておきたい」という意味が含まれます。
そのためCCを利用する場合は、きちんと意味を理解したうえで使うようにしてくださいね。ちなみに、普段のメールでCCに自分の名前が含まれている場合は返信しても問題ありませんが、情報共有の場合は返信しないほうが無難です。
不明点があれば、個別に連絡をしたほうが本筋のやりとりを邪魔せずに済むでしょう。
短時間で情報をチェックできる本文にする
わかりやすい情報共有メールのポイントは、短時間で情報をつかめる本文にすることです。結論や最も伝えたい内容は、最初に記載すればより情報を把握しやすくなります。
さらに、なるべく長文にならないよう、伝えたい内容は箇条書きにまとめ、読み手が視覚的に把握しやすいような本文にするとよいでしょう。どうしても情報量が多く長文になってしまうケースは、別でファイルにまとめて添付すると簡潔でわかりやすいメールを作成できます。
緊急度や期限を明記する
共有する情報の内容によっては、読み手のアクションが欲しいこともあるでしょう。その際は、必ず緊急度の高さや、特定の日時を明記して期限を明確にすることが大切です。
注意したいのは、緊急性の高い情報を共有する場合です。クレームの発生などで迅速な対応が求められるときは、件名に【至急】と記載してください。
ただし、使いすぎると現場に混乱をもたらす恐れがあります。情報を共有する場合は、緊急性が高いかどうかをしっかりと見極めるようにしましょう。
情報共有をしたもらったお礼は次の日までに伝える
情報共有メールをもらったら際、お礼やリアクションのメールはなるべく早く送るようにしましょう。
返信がすぐにできない状況でも、せめて「~日までに確認し、ご連絡します」などの旨を伝えておくと、コミュニケーションが滞る心配がありません。
メールで間違えやすい敬語には注意
情報共有をメールで行う際、敬語を正しく使えているのか不安になるときがありますよね。ここでは、メールで間違えやすい敬語表現について簡単にまとめてあるので、ぜひ参考にしてみてください。
目上の人に対する敬称の誤り
目上の人に対して適切な敬称を使うことが求められます。例えば、社長に対して「さん」をつけるのは明らかに適切ではありませんよね。相手の地位や役職に応じた敬称を使用しましょう。
尊敬語と謙譲語の混同
尊敬語と謙譲語は異なる敬語の形式ですが、混同されることがあります。例えば、「お手紙をお書きになる」は誤りです。「お手紙を書かせていただく」や「お手紙を書かせていただきます」といった表現を使いましょう。
敬語の過剰な使用
敬語は相手に対する敬意を示すために使われますが、過剰に使いすぎると堅苦しさや遠慮が伝わる場合があります。相手との関係性や状況に応じて、敬語の程度を調節しましょう。
メールよりビジネスチャットを使った方が効率的な理由
情報共有は、メールよりもビズネスチャットを使って行ったほうが効果的です。
ビジネスチャットを導入している会社の数は増加傾向にあり、伊藤忠テクノソリューションズ株式会社が調べたところによると、今や大手企業の3割程度が利用するまでになっています。
では、どのような店でビジネスチャットの方が効率的なのでしょうか?
要件をより端的に伝えることができる
ビジネスチャットはメールよりも端的に情報を伝えることができます。
メールでは定型文として「お世話になっております。~の誰々です。」から始めるケースが多いかと思いますが、それを煩わしいと感じている方も少なくないのではないでしょうか。
ビジネスチャットではそのような定型文を使う必要はなく、伝えたい内容だけをサクッと書いて送信することができます。
一日になんどもやり取りをするわけですから、ビジネスチャットを使うことによってかなりの時間が短縮されることでしょう。
送信後に内容を編集することができる
全てのビジネスチャットに付いているわけではありませんが、SlackやChatWorkなどの代表的なビジネスチャットツールには、送信後の編集機能が付いています。
これによって、送信する前に誤字脱字がないかのチェックを厳かに行なう必要がなくなり、送信するまでのスピードが上がります。
また、メールだと送信した内容に間違いがあった場合、改めて新しいメールを送り直さないといけないですが、ビジネスチャットだと送信内容をそのまま編集することができるので、内容がかさばることもありませんね。
ccを付けなくても複数の人に共有できる
ビジネスチャットは、個人間のダイレクトメッセージも可能ですが、複数人が参加しているグループでのメッセージが基本です。
そして、そのグループの中でメンションを付けることによって、特定のメンバーにチャットを送信することができます。つまり、ccを付けなくても自動的に複数の人に内容を送信することになります。
また、メンションが付かなかった人もグループ内の人であれば誰でもチャット内容を閲覧することができるので、より多くの人と情報共有することが可能なのです。
まとめ
社内の情報共有は、チームや企業内の業務効率や、社員一人一人の生産性を上げるためにも欠かせないものです。情報を共有する方法はメールやビジネスチャットがありますが、ツールや目的別に違いはあっても共有する情報のポイントは同じです。
簡潔にどのような点を伝えればよいのかを押さえておけば、社内の情報共有で失敗することはありません。ただし、メールやビジネスチャットで注意すべきポイントは異なるので、自分が情報共有に使っているツールごとの特徴をよく把握しておくようにしてください。
もし情報共有の内容に困った場合は、メールやビジネスチャットそれぞれの例文を参考に作成してみましょう。社内の人がすぐに情報を把握できるような内容を作成し、自分だけではなくチーム全体の業務効率の向上を目指してください。
最後に情報共有する際に役立つツール、GROWI.cloudを紹介して終わりたいと思います。
GROWI.cloudは弊社WESEEKが運営する社内wiki型のナレッジベースです。

特徴
- Markdown記法をベースに、テキストや図表もどんどん書ける強力な編集機能
- 検索エンジンにElasticsearchを採用しており、欲しい情報が早く正確に見つかる
- 料金がユーザー数に左右されない月額固定制なので、コストパフォーマンスが高い
- LDAP/OAuth/SAML など様々な認証方式に対応しており、セキュリティ性が高い
GROWI.cloudは様々な企業で導入いただいています。

- プランベーシック 月額¥5,500 25人×2app 最大50人まで
- ビジネススタンダード 月額¥15,000 75人×3app 最大225人まで
- ビジネスプロ 月額¥42,000 6app ユーザー無制限
- エンタープライズ お問い合わせ
気になった方はGROWI.cloudの詳細ページから詳しく見てくださいね。