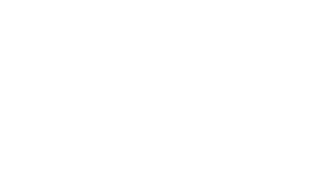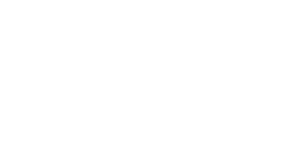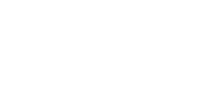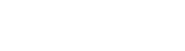業務を円滑に行うためには、情報共有ツールが効果的?!メリットやおすすめのツールを紹介

Contents
業務を円滑にする鍵は情報共有にある?!
昨今多くの企業がDXに取り掛かり、業務の円滑化を進めようとする気運が高まっていますが、なかなか業務の円滑化が上手くいかなくて困っている企業も少なくないのではないでしょうか?
業務を円滑にする方法はいくつかありますが、その中でも特に大きな効果があるのは、情報共有を効率化することです。
一人で完結するタスクを除いて、情報共有は業務を行う上で必ず必要な工程です。業務中にわからないことを他の人に聞いたり、業務の進捗を報告したりと、様々な場面で情報共有は行われていますよね。
この情報共有が円滑に行われるような環境であれば当然、業務も円滑にすすむことでしょう。
情報共有ツールによって情報共有がどのように改善されるのか
続いて、情報共有ツールを活用することによって、普段の情報共有がどのように改善されるのかをもっと具体的に見ていきましょう。
情報共有の時間が大幅に短縮
まず情報共有にかかる時間が大幅に短縮されます。
情報共有ツールを使わない場合、何か情報を得たいとき、人に聞いたり、紙の資料をあさったりしてしなければならず、時間がかかってしまいますよね。しかし、情報共有ツールには検索機能がついており、必要な情報を簡単に探し出すことができます。
自分が情報を探す時間が短縮されるのはもちろんですが、人に聞いたりするときに奪ってしまう相手の時間もなくなるので、大幅な時間短縮が実現されるのです。
業務引き継ぎの効率化
社内のメンバーが会社を離れていくとき、業務の引継ぎが発生しますよね。そのようなときにも、情報共有ツールは大きな効果を発揮します。
前任のメンバーが退職する直前までにやっていたことを情報共有ツールに記録しておけば、後任のメンバーはその記録をたどることで、効率的にキャッチアップすることができるのです。
確かに、業務の引継ぎを全て情報共有ツールで完結するのは難しいかもしれません。ですが、情報共有ツールを使えば、今まで口頭の説明やデモンストレーションで直接的に伝えなくてはいけなかったことを大幅に減らすことができるのです。
またそれだけではなく、引継ぎが完了した後、後任メンバーが業務でつまづいたとき、情報共有ツールに蓄積された前任メンバーの知見をいつなんどでも参照することができるというメリットもあるのです。
新人研修の簡略化
新しいメンバー社内に入ってきたときに、マナー研修や企業文化の説明などを行うかと思いますが、一連の研修を毎回行うのは面倒くさいと感じている方もいるのではないでしょうか?
情報共有ツール使えば、口頭で絶対話さないと伝わらない箇所以外なら、それら全てを完結させることができるのです。
実際に弊社WESEEKでも実践しています。新人研修マニュアルはGROWIにアップロードされており、新しく入社したメンバーは各自それ読んで大半の新人研修を終えます。読んだらわかるものは各自読んでもらい、口頭で説明が必要な箇所だけ教えてもらう形なので、時間効率が大幅に改善されていると個人的にも実感していますね。
情報共有ツールのさらなるメリット
実効性のある情報共有にはツールの導入がおすすめです。情報共有ツールとはどういったものなのか、または導入する際のメリットが明確に考えがつかない方もいると思います。ここでは、社内に情報共有ツールを導入する利点や、選ぶ際の要点を解説していきます。
業務の属人化を防げる
情報共有を行うことで、業務が可視化されるため業務の偏りがなくなり、作業の効率がよくなります。特定の人たちに知識が偏るのではなく、社内全体に蓄積されることで全員が業務についての知識や情報を得ることができ、社員全体の能力を高めることが可能になります。
ナレッジの蓄積が可能
情報共有ツールを使うことで、日々の業務から得た情報や気づいたことなどを残しておくことができます。メモや紙文書に記載してしまうと、全ての社員に情報が共有しきれない可能性がありますが、ツールを活用することで、全てのユーザー会員が情報に触れることが可能となります。
このようにナレッジやノウハウをツールを利用して共有しておくことで、業務の属人化も防ぐことができます。
情報管理が簡単になる
ほとんどの情報共有ツールはオンライン上で情報管理が行われているので、 一元管理することができます。また、ラベル機能などによって、必要な情報を必要な時に簡単に探し出すことが可能です。
安全対策の観点でも、情報公開の範囲やアクセス権限の設定することによって、セキュリティを強化することもできます。
多様な働き方にも対応
コロナウイルス感染拡大の影響で、今まで以上にテレワークや時差出勤を実施している企業が多くあると思います。これまではオフィスに出社して仕事をするのが日常で、情報共有は口頭やメールで行われていました。しかし、働き方が多様化している中で、以前と同じ方法で情報共有することは難しくなりました。
オンライン上で管理できるツールを導入することによって、社外からでも社内のフォルダにアクセスできたり、場所を問わず誰でも同じレベル感で仕事をすることができます。
情報共有ツールの種類
社内wiki
社内の情報をWikipediaのような形式でまとめることができるツールのことです。ドキュメントを作ることはもちろん、画像/動画ファイルをアップロードしたりすることもでき、包括的な情報管理が可能です。
こちらの記事で社内wikiについて詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてくださいね。
ファイル管理ツール
ファイルの整理/共有に特化したツールです。普段からWindowsのエクスプローラーでファイルを管理をしている方もいると思いますが、ファイル管理ツールを使えばパソコンの容量を気にすることがなく、ファイルを保存することができます。また検索性に優れているメリットもあり、必要な情報をもっと簡単に見つけることができます。
社内SNS
社内のメンバー内でチャットなどのやり取りができるツールです。代表的なものでいえばSlackなどがあります。業務中に生じた疑問をチャンネル内で投げて回答をもらったり、思いついたことをつぶやいてメンバーに共有したり、対話形式の情報共有が可能になります。
タスク管理ツール
チームで業務を行う際、他のメンバーの進行状況を把握したいですよね。そんなとき、このタスク管理ツールがあればメンバー全員のタスク進捗を一括で確認することができます。
また、タスクが進行していくにつれてタスクの優先順位なども変わってくると思いますが、そのようなときもこのツールがあれば、タスクの優先順位を可視化することができます。
顧客管理ツール
企業が顧客に対して営業やマーケティングを行っていくうえで、顧客との良好な関係を築くのに役立つツールです。以下の2種類があります。
- CRM
- 顧客との関係性を管理するためのツール
- 既存顧客に対して有効
- 顧客との関係性を管理するためのツール
- SFA
- 営業支援ツール
- 新規の潜在顧客に対して有効
- 営業支援ツール
Web会議ツール
リモートワークなどで離れた距離にいるメンバーとミーティングを行う際に役立つツールです。代表的な例でいうと、zoomやgoogle meetなどがあります。チャット形式ではなく実際の声を聞きながら情報交換できるので、文面では伝えきれない複雑な内容を共有したいときに便利ですね。
社内ポータル
社内ポータルはこれまでご紹介した社内SNSやタスク管理に加えて、ワークフローや掲示板などの便利な機能が集約されている社内向けツールです。その代表例としてはTUNAGがあります。
社内の情報を一元化することで、社員間の情報共有が活発化し、業務効率の向上が期待できるでしょう。
ツールを選ぶ際のポイント
必要な機能は備わっているか?
情報共有ツールには主に、ドキュメントの共有、タスクやスケジュールの管理、チャットやweb会議などの機能が備わっています。企業によって、必要な機能とそうでない機能があると思います。
プロジェクトを管理することを目的として使うのであれば、タスク機能がより有用であるツールを探すなど、ツールに何を求めるのかを考え、作業環境にあったものを選ぶ必要があります。
様々なツールがあり、それぞれ備わっている機能や料金が異なるため、自社のニーズと合っているのかを確認しましょう。
操作性は良いか?
社内の全体が ITツールに使い慣れているとは限りません。ユーザーとなる社員のITリテラシーに合わせてどちらのツールにするかを決めることも重要です。
実際に使っていく上で、使いやすさというのは重要です。ツールの利用を定着させるためにも、機能を犠牲にして使いやすさを優先した方が良い場合もあります。
とはいえ、実際に使ってみないとわからないこともあると思うので、ほとんどのツールに用意されている無料プランやお試しプランで一度試してみて、使い勝手や操作性を実際に確かめてから選ぶことをお勧めします。
検索性は良いか?
ツールに情報が蓄積された後、検索が簡単に行うことができるのかも重要になります。大量に蓄積されたデータの中から、求めている情報が探したい時にすぐ見つけられることができるのかを確認すると良いでしょう。
候補ワード、関連ワードの表示の有無や、カテゴリやタグの使い分けなど様々な検索方法があります。キーワードでの検索スピードだけでなく、検索方法の種類や検索精度も確認しましょう。
おすすめの社内wikiツールGROWI.cloud
弊社が運営している社内wikiツールGROWI.cloudを紹介します。
主な特徴
- どれだけ利用者が増えても年額が554,400円以上になることはなく、大人数での利用に向いている
- 閲覧、編集権限がページごとに細かく設定できる
- 多彩なテーマが用意されていたり、サイドバーのカスタムができたり、自由度が高い
詳しくはこちらのページへ。
料金
大きく分けて3つのプランがあり、以下の通りです。
- ベーシック 5500円/月
- 1アプリあたりの上限ユーザー数25
- アプリ数2
- ビジネススタンダード 15000円/月
- 1アプリあたりの上限ユーザー数75
- アプリ数3(5000円/アプリ で上限2つまで追加可能)
- ビジネスプロ 42000円/月
- 1アプリあたりの上限ユーザー数無制限
- アプリ数6(オプションでいくつでも追加可能)
詳しくはこちらのページへ。
もっと効率良く情報共有するための工夫やポイントとは?
情報共有を効率化させることで、たくさんのメリットがあることをお伝えいたしました。重要性は理解されていても、自分で実際に行動に移す際に何が問題でどのように対応していくべきなのかわからないという方々もいらっしゃると思います。
より効率よく情報共有を行うための具体的なポイントや工夫をご紹介いたします!
情報共有の重要性の理解促進
まず最初に、会社全体で情報共有をする目的を再確認し、情報共有の必要性を理解してもらうことが重要です。情報共有は一部の人たちだけで行ってもあまり効果が得られません。なので組織全体が情報共有をすることで得られるメリットなどの理解促進を図り、社員の意識改革をする必要があります。
情報共有しやすい環境整備
積極的な情報共有や、コミュニケーションを活性化させていくためにも、役職など関係なく誰もがためらいなく気軽に共有できる組織風土をつくっていくことが重要です。
情報や知識などを共有する際に、否定や批判をされる不安のない、心理的安全性の高い雰囲気づくりをしていくことが大切です。例えば、社内で配属先関係なくコミュニケーションを取ることができる機会や場所を設けて、良好な人間関係を築けるように環境を整えると良いでしょう。
このように内的な部分も整えていくと、情報共有がより効率化されるでしょう。
共有方法やルールを定める
情報共有のルールや指標が設定されていないと、情報共有の優先度が人によって異なってしまい、社内で情報共有が浸透しません。 ある程度のルールがないと、情報にばらつきが生まれてきてしまいます。
またルールを設定する際に、難しくしすぎたり数が多くなってしまうと情報が停滞していまい、情報共有自体に時間がかかってしまいます。細かすぎる基準を設けてしまうと、情報共有をすることを面倒と感じさせてしまう可能性があるので、明確で簡単なルールを作るように意識する必要があります。
例えをあげると、情報をカテゴリー別に分けて共有するスペースを決めたり、共有するべき項目やタイミングなどを明確にしておくとです。さらに、簡単にルールに従うためにテンプレートを作成しておくなど工夫を施すことも良いでしょう。
まとめ
ここまで、円滑な業務には円滑な情報共有が大事であることを解説してきました。
円滑な情報共有を実現するには、情報共有ツールを導入することがおすすめです。情報共有ツールは様々な種類がありますが、弊社の運営するGROWI.cloudは社内wikiが初めてという方にも簡単にお使いいただけます。
ご興味がある方はぜひトライアルしてみてくださいね!