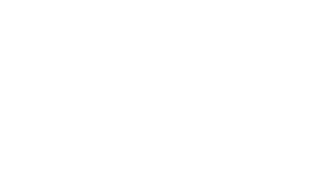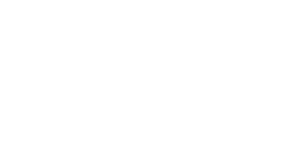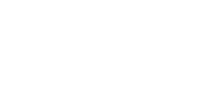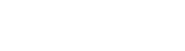上司が情報共有しない!その理由と具体的な対処法を5つご紹介

仕事をスムーズに行うのに必要不可欠な情報共有。上司が情報共有してくれない場合どうしたらいいのか、考えられる相手の心理と対処法を詳しくご紹介します。
上司が情報共有しない理由
なぜ情報共有しないのか、上司がどんなことを考えているのか気になりますよね。考えられる理由を5つご紹介します。上司の様子や傾向などから、当てはまるものがないか探してみてください。
関連記事: 情報共有しない同僚に皆悩んでる!教えたくない心理とは?
情報共有の必要性を知らない
業務上必要な情報を社員やスタッフ全員が知っておくことは仕事を進める上で大切です。しかし、長きにわたって情報共有をしてこなかった上司の場合、情報共有の必要性自体を知らない可能性があります。
凝り固まった考え方を持っている、自身の価値観を変えることに抵抗がある上司もいます。情報共有の必要性を理解していなければ、当然、情報共有の優先順位は低くなります。他の業務を優先することで、結局は情報共有されない事態に陥ってしまうのです。
社員には情報共有するけれど、アルバイトやパートのスタッフには共有しないというケースもあります。一緒に仕事をするのですから、雇用形態にかかわらず全員で情報を共有することが必要ですが、上司がそれを理解していない可能性もあります。
関連記事:チームにおける情報共有の重要性:上手くいっているチームには特徴があった!?
部下に任せられないと思っている
部下や他人を信用していないので、情報共有しない可能性もあります。自分より経験や知識の少ない部下に任せられないと考えていると、情報共有するという発想にはならないでしょう。
会社は組織であり、個人が協力し合うことが必要です。協力することでよりよい仕事ができ、仕事を任せることで部下は育ちます。ただし他人を信頼していない上司は、そもそも協力する気がない可能性があります。秘密主義である、一人で仕事を抱え込みやすい上司の場合、他人を信用していない傾向があるかもしれません。
自分だけが知っていることに優越感を感じている
他の人が知らない情報を知っていると、周囲から特別な存在に見られることがありますよね。特別な存在に見られることに優越感を感じており、意図的に情報共有をしないケースもあります。周囲から一目置かれる存在でありたい、自分が優位に立ちたいと考える傾向のある上司だと、このような理由が考えられます。
周囲の人が知らない情報は、周囲に知れ渡ると価値が下がると考えている上司もいます。しかし、意図的に情報共有をしないことで業務に支障をきたす恐れもあります。
情報共有を手間に感じている
情報共有の必要性や得られるメリットはある程度認識しているものの、情報共有するという工程自体が面倒で、避けてしまうパターンです。対面や電話で話しをすると情報をくれるけれど、メールやツールを使ったやりとりはあまりしないというケースも同様です。
情報共有のためのツールはたくさんあり、シンプルで簡単に使えるものも多いですが、ツールの使い方に慣れていない、新しいものに抵抗があるなどの理由で情報共有自体を面倒に感じている可能性があります。
関連記事:情報共有がうざいと感じる人の心理とは?原因と対策をあわせてご紹介
嫌がらせやパワハラによるもの
あってはならないことですが、さまざまな人が働く会社では嫌がらせやパワハラで情報共有をしない上司がいるケースもあります。特定の人に意識的に情報共有をしない、情報を与えないという行為は、嫌がらせです。情報不足で業務に支障が出てしまい、そのことで上司から責められる場合もあります。
情報共有しない上司と働くデメリット
仕事をする上で情報共有は不可欠です。情報共有をしない上司と働くことは、どのようなデメリットがあるのでしょうか。
効率的に仕事ができない
業務をスムーズに進めるためには、必要な情報をチーム全員で共有することが大切です。情報を知らなかったことで作業が二度手間になる、仕事に時間がかかるなど、効率が下がってしまいます。お互いの仕事内容や進捗状況が把握できず、円滑な業務の遂行を妨げる恐れもあります。
一度起きたミスやミスの原因をチーム内で共有していれば、同じミスが起きることを防げますよね。情報共有を怠るとミスやトラブルも起こりやすくなります。非効率な仕事は生産性の低下を意味しています。同じ作業に対して余計な時間がかかり、不必要な費用が発生することで、時間やコストが浪費され、無駄な残業を余儀なくされる可能性もあるでしょう。
成長スピードが遅い
上司が持っている知識やノウハウ、積み重ねてきた経験からわかることなどを部下に共有することは、部下の成長につながります。会社の戦力として活躍できるようになるためには、会社や上司が持っているノウハウの共有も大切です。ノウハウを共有することで、さらに高度な業務へつなげることもできます。
自分で考えて行動することが求められる場面もありますが、そもそも教えていなければできないこともあります。自己流で仕事をするには限界があり、組織としての発展も見込めないでしょう。情報共有してもらえない場合、限定された範囲での成長しか見込めず、わからないことを調べるために時間を費やすことで成長スピードが遅れてしまう可能性があります。
上司との関係に悩まされる
上司が情報共有をしてくれないと「自分のことをよく思っていないのでは」「信頼されていないのでは」「会社の一員として認められていないのでは」と心配になることもあるでしょう。意図しているか意図していないかにかかわらず、情報共有されないと嫌な気持ちになってしまうこともありますよね。自分にだけ情報共有してくれないなど、嫌がらせが明らかな場合、良好な人間関係の構築ができなくなります。
もし、入社したばかりであれば、仕事を覚えるだけでも大変です。そんな中で上司に不信感や嫌悪感を持つ、上司と関わることにストレスを感じるなど、業務以外のことで頭を悩ますことになると負担が大きくなります。事態が重い場合、離職の原因にもなるでしょう。
上司に情報共有してもらうための対処法5つ
仕事をスムーズに、効率的に進めるためにも情報共有は必要です。情報共有しない上司に情報共有してもらうために試してみてほしい方法を5つご紹介します。
まずは自分から情報共有する
「情報共有してほしい」と上司に直接伝えることに抵抗がある場合は、行動で示してみましょう。自分から積極的に情報共有をすることで、上司が情報共有のメリットや必要性に気付く可能性があります。情報共有の必要性を知らない上司であればなおさらです。
お客様の情報や自分の仕事の進捗状況、上司にとって有益と思われる情報など、業務上必要な情報は積極的に上司に共有しましょう。できれば自分だけでなく、同僚など自分以外の社員にも同じような行動をしてもらうとより効果が期待できます。
情報共有するということは、上司とのコミュニケーションにつながるので、関係性の構築にも効果的といえます。
関連記事:情報共有における適切な敬語の使い方とは?例文を用いて徹底解説
情報共有を提案する
自分のやる気を見せた上で、上司に情報共有してほしいと提案する方法です。上司は、今まで行っていなかったことを始めるため、時間を割く必要があります。「情報共有してください」というだけでは、上司もあまり気がのらないかもしれませんが、仕事に対するやる気や向上心をアピールすることで前向きに捉えてくれる場合もあるでしょう。
ただ、提案する際のいい方には注意が必要です。「上司が情報共有しないから、非効率な状態になっている」といった上司を責めるようないい方はNGです。情報共有することでチームとして効率的に動けること、上司自身にもメリットがあることなど、前向きな言葉で伝えます。
上司とコミュニケーションをとる
仕事上で必要な最低限の会話しかしていない場合、あまりお互いのことを知らない可能性があります。信頼関係を築くためには、コミュニケーションを大切にしましょう。
目を見て挨拶すること、はっきりと返事をすること、業務上の報告や相談をすることは基本です。ちょっとした世間話や、ランチタイム、移動時間などに上司と会話することで、上司がどんなことを考えているのか、どんな価値観を持っているのかを知ることができます。
わからないことがあれば上司にアドバイスを求め、指摘されたことはすぐに実践し、その結果を報告することで信頼関係を築いていけるでしょう。上司と良好な関係を築けていれば、情報共有をしてほしいという提案もしやすくなります。
情報共有できる仕組みをつくる
そもそも情報共有できる仕組みがなければ、情報共有ができません。情報共有したい気持ちはあるけれど、仕組みがないためできていない可能性もあるのです。紙ベースやメールなどを使った情報共有の効率が悪いと感じ、情報共有すること自体が面倒に感じている場合もあります。
紙ベースの情報共有は、やり取りに時間や手間、コストがかかり、必要な情報を検索したいときも効率が悪いです。メールの場合は当人同士のやり取りのため、宛先に含まれている人にしか情報共有されません。
情報共有に便利なツールを活用することで、効率よく情報共有ができます。ただ、会社内に情報共有する雰囲気がない場合、ツールを整備してもなかなか活用されないことがあります。情報共有に関するルールを作るなど、情報共有を業務の一環として根付かせる雰囲気づくりも必要です。
他の社員に相談する
自分にだけ情報共有をしてもらえないなど、嫌がらせやパワハラをする上司の場合、自分だけで解決するのは難しいですよね。「嫌がらせをやめてほしい」と上司に直接伝えるのはハードルが高いでしょう。今回ご紹介した方法を試しても一向に改善が見られない場合は、他の社員へ相談する、社内もしくは社外の相談窓口に報告・相談するなど、他の人に助けを求めましょう。会社には、労働者が快適に働ける職場環境を整える義務があります。嫌がらせやパワハラは当事者だけの問題ではなく、会社全体で解決していくべき問題です。
社内情報共有におすすめなツール
情報共有におすすめのツールを3つご紹介します。情報共有の仕組みづくりや環境整備に、ぜひお役立てください。
GROWI.cloud
GROWI.cloudは弊社WESEEKが運営する社内wiki型のナレッジベースです。

特徴
- Markdown記法をベースに、テキストや図表もどんどん書ける強力な編集機能
- 検索エンジンにElasticsearchを採用しており、欲しい情報が早く正確に見つかる
- 料金がユーザー数に左右されない月額固定制なので、コストパフォーマンスが高い
- LDAP/OAuth/SAML など様々な認証方式に対応しており、セキュリティ性が高い
GROWI.cloudは様々な企業で導入いただいています。

- プランベーシック 月額¥5,500 25人×2app 最大50人まで
- ビジネススタンダード 月額¥15,000 75人×3app 最大225人まで
- ビジネスプロ 月額¥42,000 6app ユーザー無制限
- エンタープライズ お問い合わせ
NotePM
NotePMは、株式会社プロジェクト・モードが運営するナレッジマネジメントツールです。

特徴
- Word・Excel・PDFなど、ファイルの中身も全文検索
- ページを見た人・参照時間の閲覧履歴を一覧表示
- フォルダとタグで情報整理
Slack
Slackとは、Slack Technology社が開発したビジネスチャットツールです。

特徴
- メンバーを自由に選んで、チャットグループを作成することが可能
- 拡張性が高く、連携できるアプリケーションの種類が豊富
- 有料プランもあるが、無料で十分な機能を使うことができる
まとめ
情報共有は業務をスムーズに進めるために必要なことです。もしも上司が情報共有しない場合、上司が情報共有の必要性を知らない、部下を信用しないタイプ、情報共有自体を面倒に感じている可能性があります。また、あってはならないことですが、嫌がらせであるケースもあります。
情報共有しない上司と働くことには多くのデメリットがあります。情報共有してもらえるように、仕組みや環境づくりなど今回ご紹介した方法を試してみてはいかがでしょうか。