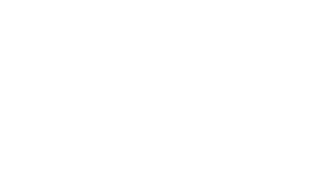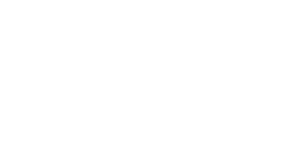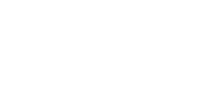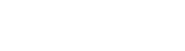ナレッジとは:ビジネスやIT、シーンごとで意味がどう違うの?

ビジネスシーンで「ナレッジマネジメント」や「ナレッジ共有」などの言葉をよく耳にする機会があるかと思いますが、そもそもの「ナレッジ」とはどのような意味なのでしょうか?
本記事では、ナレッジの言葉の意味だけに留まらず、ナレッジの使い方、ナレッジマネジメントなどについても詳しく解説していきます。
Contents
ビジネスシーンやITで、ナレッジはどのような意味になる?
ナレッジの本来の意味
ナレッジとは、英語「knowledge」をカタカナ表記にした和製英語で、辞書に沿った忠実な意味としては「知識」や「知見」などを指します。
ビジネスにおけるナレッジの意味
ビジネスで用いられる「ナレッジ」は少し意味合いが異なり、"企業にとって価値がある"知識や知見のことを指します。
とある企業に勤めるAさんがいたとしましょう。この場合、Aさんが持っている知識の中で「ナレッジ」と呼んで良いものは例えば、顧客に関連する情報やオフィスの避難経路などですね。
どちらも、勤め先の企業にとって価値のある情報だと簡単に理解できるでしょう。
では、例えばAさんが恐竜について詳しいとします。この場合はどうでしょう。
確かにプライベートにおいては、彼は恐竜について博識、つまりナレッジがあると言えますが、企業にとっては有用な知識とは言い難いですよね。この例の場合では、Aさんの恐竜についての知識は、ビジネスシーンではナレッジとは呼べないものになります。
ITにおけるナレッジの意味
ITにおけるナレッジも、基本的にはビジネスにおけるナレッジの意味と変わりません。
要は、その知識が「価値があるかどうか」です。例えば、プログラミングに関する知識やセキュリティに関する知識は価値のある知識なので、十分ナレッジと呼ぶことができるでしょう。
類語「ノウハウ」や「スキル」との意味の違い
ナレッジの類語に「ノウハウ」や「スキル」などがありますが、意味が似通っていてどれを使えばいいのか迷ってしまうことはありませんか?
ここでは、それぞれの語句の違いを見ていきます。
ナレッジとノウハウの違い
ノウハウとは英語にすると「know-how」、すなわち「何かのやり方または方法(how)を知っていること(know)」を意味します。
ノウハウという概念を最初に学問的に考えたのは、ギルバート・ライルという哲学者だと言われています。ライルは彼の主著『心の概念』で、知識(ナレッジ)とは「事実知(knowing what)」と「方法知(knowing how)」の2つに分類できると主張しており、後者の「方法知」こそがノウハウを指しています。
簡単にまとめると、
- 知識(ナレッジ)
- 事実知
- 方法知(ノウハウ)
となり、ナレッジ>ノウハウ であることがわかるでしょう。
せっかくなので、ここで「事実知」と「方法知」のそれぞれの意味も解説しましょう。
事実知と方法知
ライルの定義によると、2つの言葉は
- 事実知
- 事実や命題、規則などに関する知識
- 方法知
- やり方に関する身体知
のように説明されています。
例えば、「彼はチェスのことをよく知っている」と言う場合、2つの意味が考えられます。1つ目は、彼がチェスのルールや歴史など、言葉で説明できる事柄について博識であるという意味であり、つまりは事実知に富んでいるということを表しています。
これに対して2つ目の例は、その人がチェスに熟練していることを言い表している場合で、要するにチェスが上手である、勝つためのコツやスキルを豊富に持っているという意味です。つまり、ここでの「知っている」は、方法知に富んでいるということになります。
ナレッジとスキルの違い
続いて、ナレッジとスキルの違いを見ていきましょう。スキル(skill)とは、実体験を通して習得される専門的な能力を指します。たとえば、「ITスキル」「エクセルスキル」といったように、個別分野に役立つ「技術」「技能」を指すのが一般的です。スキルは基本的にノウハウの一領域に分類される概念です。
それゆえ、各概念の階層構造としては一般性の高い順に、
ナレッジ>ノウハウ>スキル
となります。
ビジネスシーンでよく使われる「ナレッジ」を含む関連語句
「ナレッジ」の語句の意味が確認できたところで、次はビジネスシーンで頻出の「ナレッジ」を含む語句について紹介します。
ナレッジベース
社内の人間それぞれが持っている知識やノウハウを一か所にまとめたデータベースのことです。データベースに集まっているナレッジは、社内の人間であればだれでもアクセスすることができ、自身のナレッジとして吸収することができます。効率的な運用ができていれば、飛躍的な生産性向上が期待できるでしょう。
関連記事:ナレッジベースの意味は?メリットは?
ナレッジワーカー
企業にとって付加価値のある知識・ノウハウを生み出す人のことを指し、「知識労働者」とも呼ばれています。単に知識を創出するだけではなく、それらをまとめ上げて他の人に共有するところまでが求められます。
逆に、対義語のマニュアルワーカーは、決められたマニュアルに沿った業務を行う人のことを指し、新たな情報を生み出しません。
ナレッジトランスファー
特定のナレッジがその所有者から別の人へ移転することをナレッジトランスファーと言います。
頭文字をとって「ナレトラ」と呼ばれることもあるそうです。
同じような言葉に「スキルトランスファー」がありますが、こちらはスキル、つまり技術に関する知識の移転に用いられます。
ナレッジマネジメント
個人の知識やノウハウを組織で有効に活用できるようにすることで、日本語では「知識管理」などとも呼ばれています。業務効率の改善や新人教育のコストダウンなどの様々なメリットがあり、近年はさらに注目が高まりつつあります。
ナレッジを蓄積することによって得られるメリット
ここまで「ナレッジ」の語句の意味について説明してきましたが、実際にナレッジが蓄積されていくことで、どのようなメリットがあるのでしょうか?近年、ますます「社内のナレッジを蓄積しよう」という気運が高まっていますが、それにはちゃんとした理由があります。
ここでは、ナレッジを蓄積する3つのメリットを解説します。
業務の属人化が防げる
企業に長く勤めている人の中には、いつの間にか特定の業務を担当する人が1人だけになるという場合も見られます。その人が体調不良等で不在になってしまった時、他に担当できる人がいないため、業務がストップしてしまう恐れがあるでしょう。
しかし、もしその人のナレッジが社内に蓄積、共有されていれば他の人が代わりに担当することができるのです。業務の属人化を防ぐことができるのは、大きなメリットと言えるでしょう。
顧客満足度が向上する
お客様の中には、要望やクレームの対応が複数部署にわたることもあります。この際に、企業内で過去のクレームの対応方法やお客様に関する情報が共有できれば、お客様へのスムーズな対応が可能となります。より迅速でお客様の要望に合った対応ができれば、二次クレームの防止につながるだけでなく、顧客満足度の向上にもつながっていくでしょう。
人材教育が効率的になる
企業に属したばかりの新人に対するナレッジをまとめておくことで、人材育成の進捗の把握がしやすくなり、より効率良く高水準の技能や知識を会得することが可能となります。
他にも、業務について分からないことがある際に、自分で業務に関するナレッジを手に入れることができれば、ある程度の段階までは業務を行うことが可能となります。
自分で分からないことを調べ、要点を上司に確認するフローが確立できれば、より能動的に動ける社員の育成や、教育担当の負担の削減にもつながるでしょう。
貯めたナレッジをマネジメントして有効活用しよう
貯めたナレッジを有効活用するためには、ナレッジマネジメントを行うと良いでしょう。
ここでは、「ナレッジマネジメントとは何なのか」から、ていねいに解説していきたいと思います。
ナレッジマネジメントとは
ナレッジマネジメントとは、各々が持っている知識やノウハウを組織の中に蓄積していき、みんなで有効に活用していくことです。
個人が持っていた情報が他の人にも共有されることで、業務の属人化を防ぐことができたり、業務を効率化することができるのです。
ナレッジマネジメント進め方
ナレッジマネジメントを実施するにあたっては、どのような流れで進めればいいのでしょうか。以下では、ナレッジマネジメントの流れと手順を説明していきます。
企業理念とビジョンの明確化
ナレッジマネジメントを実施するにあたっては、最初に経営トップが自社の企業理念やビジョンを従業員に対して明確に示すことが大切です。これはつまり、何を目指してナレッジマネジメントを行うのか目標を明確にするということでもあります。
従業員の中には、ナレッジの共有を面倒臭がる人や、ナレッジを組織の中で生き残っていくための自分個人の資産と見なして共有したがらない人もいます。それゆえ、ナレッジマネジメントを始めるにあたっては、経営者自らが音頭を取って、トップダウン方式で強力に推進するのがおすすめです。また、取り組みの評価がしやすいように、「社内wikiの閲覧率を~%にする」というような目標値を設定することも大切です。
必要なナレッジを特定する
次のステップは、企業理念やビジョンの達成のために必要なナレッジを特定することです。ナレッジマネジメントで共有を目指すナレッジとは、ビジネスの実践現場で役に立つものでなくてはいけません。各従業員としても、「なんでもいいから知識を出せ」と言われても、困惑してしまうことでしょう。それゆえ、ナレッジマネジメントを効率的に進めるには、自社が求めるナレッジとは何かを特定し、その指針を従業員にも周知し風土づくりに努めることが必要です。
ナレッジを提供したくなる仕組みづくり
次のステップは、各従業員が自分のナレッジを進んで提供したくなる仕組みづくりに取り組むことです。ナレッジマネジメントのよくある失敗原因のひとつには、従業員の協力が得られないことがあります。それゆえ、この課題に対処するためには、ゲーム感覚でナレッジの共有を行なえる仕組みをつくるなど、従業員が積極的にナレッジを共有しやすい仕組みや企業風土をつくっていくことが大切です。
集めたナレッジの共有と活用の仕組みづくり
最後のステップは、集めたナレッジの共有や活用をしやすい仕組みをつくることです。せっかくナレッジを集めても、そのナレッジを参照する際に分厚いマニュアル本をいちいち開かないといけないとしたら、ナレッジの共有はなかなか進まないでしょう。
それゆえ、ナレッジマネジメントを成功させるには、社内wikiを活用するなどして、集めたナレッジへ容易にアクセスできるような仕組みを作ることが大切です。誰でもすぐにナレッジにアクセスできる環境を整えることで、ナレッジの維持やさらなる発展が期待できます。
ナレッジマネジメントならGROWI.cloud
GROWI.cloudは弊社WESEEKが運営する社内wiki型のナレッジベースです。

特徴
- Markdown記法をベースに、テキストや図表もどんどん書ける強力な編集機能
- 検索エンジンにElasticsearchを採用しており、欲しい情報が早く正確に見つかる
- 料金がユーザー数に左右されない月額固定制なので、コストパフォーマンスが高い
- LDAP/OAuth/SAML など様々な認証方式に対応しており、セキュリティ性が高い
GROWI.cloudは様々な企業で導入いただいています。

- プランベーシック 月額¥5,500 25人×2app 最大50人まで
- ビジネススタンダード 月額¥15,000 75人×3app 最大225人まで
- ビジネスプロ 月額¥42,000 6app ユーザー無制限
- エンタープライズ お問い合わせ
ぜひ、興味のある方はGROW.cloudをご覧くださいね。
まとめ
「ナレッジ」はシーンごとに少し意味合いがことなることがわかりました。
「ノウハウ」や「スキル」などの類義語もあるので、どれを使うのが適切か、と迷うこともあるかもしれませんが、日常生活において、そこまで厳密に語句の意味の違いを意識する必要はないでしょう。
また、ナレッジを活用するためにはナレッジマネジメントが有効であることも解説しました。
ナレッジマネジメントを行う際には、ぜひGROWI.cloudの導入もご検討くださいね。